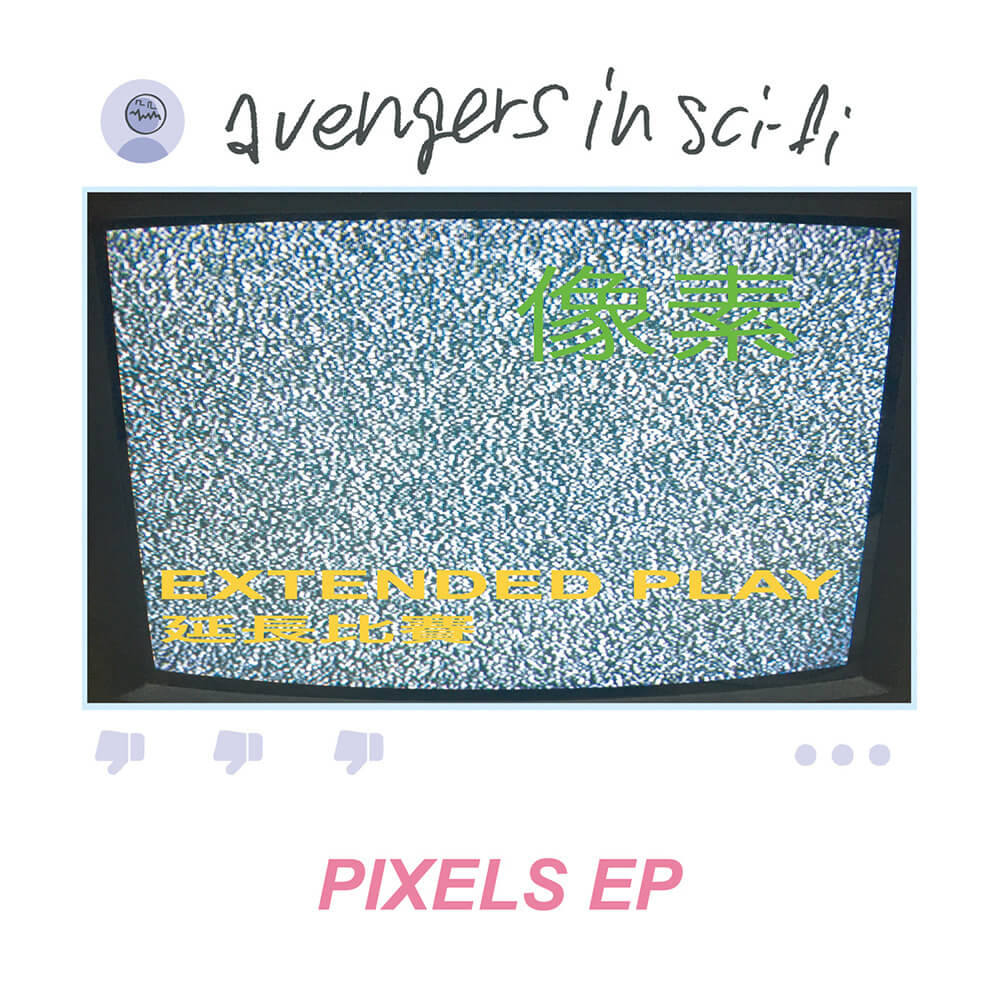Interview:Azumi×高岩遼
——Azumiさんと高岩さんは10月13日(土)に行われるハーレーダビッドソンの<FREE[ER] WEEKEND PREMIUM LIVE SHOWCASE>で、久々の共演となります。まずは、お二人の最初の出会いについて教えてください。 Azumi 昨年の4月に六本木でやったライブが初めましてだよね? 高岩遼(以下、高岩) そうですね。六本木のVARITというライブハウスでイベントをすることになって、ぜひ誰か女性のジャズ・シンガーを招きたいねという話をしていたんです。そこでライブハウスのスタッフさんから「Azumiさんがいいんじゃないか」という提案があって、自分も「Azumiさんだ!」ということでお声がけしました。 ——その時もジャズのイベントで、お二人でデュエットも披露したそうですね。 高岩 やりましたね。“Fly Me To The Moon”歌いました。キーをどうしようか、みたいな相談をしたのを覚えてます。 Azumi あと“You'd Be So Nice To Come Home To”も一緒にやったよね。 ——どちらもジャズのスタンダードですね。デュエットする楽曲はすんなりと決まったんですか?
高岩 事前にメールで、「何やります? てか、遼くんは何を歌うの?」みたいなやり取りを少しして、あとは現場で少し合わせたくらいでした。でも、どっちかというと、「何着る?」みたいな衣装の話をしてましたね。「僕、セットアップは緑ですよ」って。
Azumi そうかも(笑)。今日も何を着てくるのかすごい気になったもん。
高岩 俺もどんな感じか、結構気になってました(笑)。
——実際に共演してみて、お互いの印象はいかがでしたか?
Azumi まずは声が素晴らしいと思いましたね。日本人で、フランク・シナトラのような唱法のクルーナーってなかなかいないじゃないですか。上の世代の大先輩には多いですけど、若い方ではあまりいない。私はその時初めてジャズを歌ってるのを聴いたんですけど、素晴らしかったです。
——Azumiさんの印象はどのように変わりましたか?
高岩 それまではお会いしたことがなかったので、もっとフワフワした、フェミニンな方なのかなと思ってたんですよ。でも、実際に共演してみると男気があって。歌手として北海道の方から出てこられて、タフにやられてる。精神力の強さを感じましたね。
Azumi いやいや、ありがとうございます(笑)。
——どちらもジャズのスタンダードですね。デュエットする楽曲はすんなりと決まったんですか?
高岩 事前にメールで、「何やります? てか、遼くんは何を歌うの?」みたいなやり取りを少しして、あとは現場で少し合わせたくらいでした。でも、どっちかというと、「何着る?」みたいな衣装の話をしてましたね。「僕、セットアップは緑ですよ」って。
Azumi そうかも(笑)。今日も何を着てくるのかすごい気になったもん。
高岩 俺もどんな感じか、結構気になってました(笑)。
——実際に共演してみて、お互いの印象はいかがでしたか?
Azumi まずは声が素晴らしいと思いましたね。日本人で、フランク・シナトラのような唱法のクルーナーってなかなかいないじゃないですか。上の世代の大先輩には多いですけど、若い方ではあまりいない。私はその時初めてジャズを歌ってるのを聴いたんですけど、素晴らしかったです。
——Azumiさんの印象はどのように変わりましたか?
高岩 それまではお会いしたことがなかったので、もっとフワフワした、フェミニンな方なのかなと思ってたんですよ。でも、実際に共演してみると男気があって。歌手として北海道の方から出てこられて、タフにやられてる。精神力の強さを感じましたね。
Azumi いやいや、ありがとうございます(笑)。
 ——今回の<FREE[ER] WEEKEND>は、それ以来久しぶりの共演になります。お二人が出演される10月13日(土)のステージは<Swingin’Night>ということで、ジャズ・セットを予定されていると思いますが、まずはお二人のジャズとの出会いについて教えていただけますか?
Azumi 私はもともと10代の頃からブラック・ミュージックばかり聴いていて、70年代ソウルやファンク、90年代のアシッドジャズ、ヒップホップ、R&B、その辺にどっぷりハマった人なんです。例に漏れずローリン・ヒルになりたかったB-GIRLみたいな。
高岩 いやー、最高っすよね。
Azumi 私はローリンのつもりだったけど、アムラーって言われてた(笑)。
——(笑)。確かに、そういう時代かもしれませんね。
Azumi その辺を聴いてるうちに、その影響元でもあるジャズとフュージョンの方に向いていって。一番初めに聴いたのがディジー・ガレスピーだったのかな。エラ・フィッツジェラルドや、ヴォーカリストも聴いてはいたんですけど、それよりも実はインストものが好きだったんです。中でもハービー・ハンコックが大好きで、LAでレコーディングがあった時にハービーの家を見に行ったり(笑)。
——今回の<FREE[ER] WEEKEND>は、それ以来久しぶりの共演になります。お二人が出演される10月13日(土)のステージは<Swingin’Night>ということで、ジャズ・セットを予定されていると思いますが、まずはお二人のジャズとの出会いについて教えていただけますか?
Azumi 私はもともと10代の頃からブラック・ミュージックばかり聴いていて、70年代ソウルやファンク、90年代のアシッドジャズ、ヒップホップ、R&B、その辺にどっぷりハマった人なんです。例に漏れずローリン・ヒルになりたかったB-GIRLみたいな。
高岩 いやー、最高っすよね。
Azumi 私はローリンのつもりだったけど、アムラーって言われてた(笑)。
——(笑)。確かに、そういう時代かもしれませんね。
Azumi その辺を聴いてるうちに、その影響元でもあるジャズとフュージョンの方に向いていって。一番初めに聴いたのがディジー・ガレスピーだったのかな。エラ・フィッツジェラルドや、ヴォーカリストも聴いてはいたんですけど、それよりも実はインストものが好きだったんです。中でもハービー・ハンコックが大好きで、LAでレコーディングがあった時にハービーの家を見に行ったり(笑)。
 高岩 マジっすか!(笑)。ヴォーカリストじゃないのは意外ですね。
Azumi そうなんですよ。自分はヴォーカリストなんだけど、聴くのはインストの方が多い。ドラムとベースとバッキング。リズムやコード感ばかりに耳が行ってました。
——高岩さんはどのようにジャズと出会ったんですか?
高岩 俺は小学校3年生くらいの時に、スティーヴィー・ワンダーの『The Definitive Collection』っていうアルバムをずっと聴いてて。それこそ歌詞カードがグシャグシャになるくらい聴き込むほど大好きだったんです。その後、小学校6年生くらいでレイ・チャールズに出会って。
Azumi えー! 早熟!
高岩 “We Are The World”の一番最後のパートを歌ってるので、感激しちゃって。中学校に入るとヒップホップがやってきて、ヒップホップ、R&B、ソウル、ブルースみたいな。本当に黒人音楽至上主義みたいな脳みそのB-BOYでしたね。
——十代の頃の音楽ヒストリーは、お二人ともどこか似てますね。
高岩 B-GIRLとB-BOYだったっていう。共通してますね(笑)。
Azumi そうですね(笑)。皆、やっぱり入りは「ブラック・ミュージック!」みたいなところあるよね。『ブルース・ブラザーズ』とか観るといまだに興奮します。
高岩 高校2年生くらいでブルースとかジャズを聴くようになるんですけど、その時はジャズとブルースの境目がまだ分からなかったんですよ。それで、ある時に手に入れたジャズ・ヴォーカリストの廉価盤コンピレーションに、一人めちゃくちゃ歌が上手い人がいて、感激して号泣しちゃったんですよ。それがフランク・シナトラだったんですよね。心に届くものがあると。最高で、そこからジャズのヴォーカルはずっと聴いてましたね。
高岩 マジっすか!(笑)。ヴォーカリストじゃないのは意外ですね。
Azumi そうなんですよ。自分はヴォーカリストなんだけど、聴くのはインストの方が多い。ドラムとベースとバッキング。リズムやコード感ばかりに耳が行ってました。
——高岩さんはどのようにジャズと出会ったんですか?
高岩 俺は小学校3年生くらいの時に、スティーヴィー・ワンダーの『The Definitive Collection』っていうアルバムをずっと聴いてて。それこそ歌詞カードがグシャグシャになるくらい聴き込むほど大好きだったんです。その後、小学校6年生くらいでレイ・チャールズに出会って。
Azumi えー! 早熟!
高岩 “We Are The World”の一番最後のパートを歌ってるので、感激しちゃって。中学校に入るとヒップホップがやってきて、ヒップホップ、R&B、ソウル、ブルースみたいな。本当に黒人音楽至上主義みたいな脳みそのB-BOYでしたね。
——十代の頃の音楽ヒストリーは、お二人ともどこか似てますね。
高岩 B-GIRLとB-BOYだったっていう。共通してますね(笑)。
Azumi そうですね(笑)。皆、やっぱり入りは「ブラック・ミュージック!」みたいなところあるよね。『ブルース・ブラザーズ』とか観るといまだに興奮します。
高岩 高校2年生くらいでブルースとかジャズを聴くようになるんですけど、その時はジャズとブルースの境目がまだ分からなかったんですよ。それで、ある時に手に入れたジャズ・ヴォーカリストの廉価盤コンピレーションに、一人めちゃくちゃ歌が上手い人がいて、感激して号泣しちゃったんですよ。それがフランク・シナトラだったんですよね。心に届くものがあると。最高で、そこからジャズのヴォーカルはずっと聴いてましたね。
 ——高岩さんは、10月17日にソロ・デビュー・アルバム『10』のリリースを予定されています。このアルバムはどのような作品になっていますか?
高岩 シナトラのカバー3曲で、後は全部オリジナルです。フルでビッグ・バンドでレコーディングしたんですけど、僕の中のジャズ最先端になってます。僕のジャズ愛だけだったらシナトラの焼き直しとかレイ・チャールズみたいになってしまいそうだったんですけど、〈Tokyo Recordings〉のYaffleがプロデューサーで入ってくれて、今までチャレンジしたことがなかったような作品になりました。
——今回ソロ・アルバムを作ったのは、どういうきっかけがあったんですか?
高岩 もともと岩手の田舎から「絶対スターになりたい」って思いで上京してくるときに、母ちゃんとか仲間に「俺が絶対にソロで出すときはビッグ・バンドでしかやらない」って話をしていたんです。それから音大で四年間ジャズを学んで、卒業してからSANABAGUN.とかTHE THROTTLEとか、SWINGERZって仲間たちが増えていく中でも、ソロの思いはずっと頭にあって。でも、僕が首謀者でバンドを作ってるんで、男としての責任があるじゃないですか。だから、まずはバンドを盛り上げていたんですけど、去年の4月くらいに、〈ユニバーサル〉のユウスケくんが、「遼くんソロやらない?」っていうのを恵比寿BATICAで言われて、「よし、じゃあビッグバンドでやろう!」って話したんです。
Azumi いい話ですね!
——高岩さんは、10月17日にソロ・デビュー・アルバム『10』のリリースを予定されています。このアルバムはどのような作品になっていますか?
高岩 シナトラのカバー3曲で、後は全部オリジナルです。フルでビッグ・バンドでレコーディングしたんですけど、僕の中のジャズ最先端になってます。僕のジャズ愛だけだったらシナトラの焼き直しとかレイ・チャールズみたいになってしまいそうだったんですけど、〈Tokyo Recordings〉のYaffleがプロデューサーで入ってくれて、今までチャレンジしたことがなかったような作品になりました。
——今回ソロ・アルバムを作ったのは、どういうきっかけがあったんですか?
高岩 もともと岩手の田舎から「絶対スターになりたい」って思いで上京してくるときに、母ちゃんとか仲間に「俺が絶対にソロで出すときはビッグ・バンドでしかやらない」って話をしていたんです。それから音大で四年間ジャズを学んで、卒業してからSANABAGUN.とかTHE THROTTLEとか、SWINGERZって仲間たちが増えていく中でも、ソロの思いはずっと頭にあって。でも、僕が首謀者でバンドを作ってるんで、男としての責任があるじゃないですか。だから、まずはバンドを盛り上げていたんですけど、去年の4月くらいに、〈ユニバーサル〉のユウスケくんが、「遼くんソロやらない?」っていうのを恵比寿BATICAで言われて、「よし、じゃあビッグバンドでやろう!」って話したんです。
Azumi いい話ですね!
 ——Azumiさんもソロでは、ジャズ・アルバムのリリースやジャズ・フェスの出演など、ジャズ・シンガーとしての自分を大切にされている印象があります。
Azumi 私もwyolicaをやってる頃から、ずっとジャズ・アルバムを出すのが夢だったんですよ。でもwyolicaの時は、創ることができなくて我慢してたんですけど、ある時自分で企画を立てたんです。
——その企画はどのように発案したんですか?
Azumi ジャズってなんで若い女の子たちが聴かないのかな? という疑問がずっと自分の中にあったんです。ジャズは敷居が高いし、難しい音楽みたいな印象があるから、私はその入り口を作りたいなと思って。それで、ジャズ・スタンダードやクラシックのメロディに自分で日本語詞を乗せるというコンセプトにしました。あとは、ジャズ・シンガーって夜のイメージが強いけれど、朝聴けるジャズにしようと。ジャズの間口が広くなって、ジャズを知るきっかけになれば良いなと、思っています。
——ハーレーダビッドソンとの関連でいうと、毎年開催されているハーレー乗りの祭典<BLUE SKY HEAVEN>に、お二人とも出演されてますよね。全国から集まったハーレー・オーナーの前でのライブはいかがでしたか?
Azumi 多分私のことを知っている人はほとんどいなかったと思うんですけど、なんか優しかったし、温かかったです。「良かったよ、ねーちゃん!」みたいな感じで(笑)。
高岩 みんな優しいですよね。
Azumi 見た目はみんなゴツいのに、優しい。
——Azumiさんもソロでは、ジャズ・アルバムのリリースやジャズ・フェスの出演など、ジャズ・シンガーとしての自分を大切にされている印象があります。
Azumi 私もwyolicaをやってる頃から、ずっとジャズ・アルバムを出すのが夢だったんですよ。でもwyolicaの時は、創ることができなくて我慢してたんですけど、ある時自分で企画を立てたんです。
——その企画はどのように発案したんですか?
Azumi ジャズってなんで若い女の子たちが聴かないのかな? という疑問がずっと自分の中にあったんです。ジャズは敷居が高いし、難しい音楽みたいな印象があるから、私はその入り口を作りたいなと思って。それで、ジャズ・スタンダードやクラシックのメロディに自分で日本語詞を乗せるというコンセプトにしました。あとは、ジャズ・シンガーって夜のイメージが強いけれど、朝聴けるジャズにしようと。ジャズの間口が広くなって、ジャズを知るきっかけになれば良いなと、思っています。
——ハーレーダビッドソンとの関連でいうと、毎年開催されているハーレー乗りの祭典<BLUE SKY HEAVEN>に、お二人とも出演されてますよね。全国から集まったハーレー・オーナーの前でのライブはいかがでしたか?
Azumi 多分私のことを知っている人はほとんどいなかったと思うんですけど、なんか優しかったし、温かかったです。「良かったよ、ねーちゃん!」みたいな感じで(笑)。
高岩 みんな優しいですよね。
Azumi 見た目はみんなゴツいのに、優しい。
 ——高岩さんはどうでしたか?
高岩 僕は二つのバンドTHE THROTTLEとSANABAGUN.で出演させて頂いて。ロックとヒップホップでリアクションも全然違って、面白かったですよ。ハーレーとロックは何か繋がるものがあるし、ハーレーとヒップホップは意外性が楽しめるということで、そういうのがお客さんの顔見てわかるというか。「懐かしいことやってるねぇ! サイン書いてくれよこのGジャンの後ろに!」みたいなおじいちゃんいたし(笑)。
Azumi (笑)。遼くんは、ヤンチャだったおじいちゃんとかに好かれそうだね。
——今回の<FREE[ER] WEEKEND>は、ハーレーダビッドソンの最新モデルFXDR™ 114と過ごす特別な週末というイベントです。このFXDR™ 114を実際にご覧になった感想を教えてください。
Azumi すっごいオシャレ。フォルムが美しい。
高岩 確かに。ちょっとトランスフォームしそうですよね。形が変わって、喋りかけてきそうな雰囲気がある(笑)。
——高岩さんはどうでしたか?
高岩 僕は二つのバンドTHE THROTTLEとSANABAGUN.で出演させて頂いて。ロックとヒップホップでリアクションも全然違って、面白かったですよ。ハーレーとロックは何か繋がるものがあるし、ハーレーとヒップホップは意外性が楽しめるということで、そういうのがお客さんの顔見てわかるというか。「懐かしいことやってるねぇ! サイン書いてくれよこのGジャンの後ろに!」みたいなおじいちゃんいたし(笑)。
Azumi (笑)。遼くんは、ヤンチャだったおじいちゃんとかに好かれそうだね。
——今回の<FREE[ER] WEEKEND>は、ハーレーダビッドソンの最新モデルFXDR™ 114と過ごす特別な週末というイベントです。このFXDR™ 114を実際にご覧になった感想を教えてください。
Azumi すっごいオシャレ。フォルムが美しい。
高岩 確かに。ちょっとトランスフォームしそうですよね。形が変わって、喋りかけてきそうな雰囲気がある(笑)。
 ——高岩さんは昨年、大型自動二輪免許を取られて、今は実際にハーレーに乗ってらっしゃるんですよね。
高岩 そうです。僕とSANABAGUN.のギターの隅垣元佐が免許取らせてもらいました。
Azumi そうなんだー、すごい! でも、むちゃくちゃ似合いますね。
高岩 去年の夏に、かっこいいところを地元の奴に見せたいから、1800cc近い、デカいハーレーで地元の岩手県宮古市に凱旋帰省したんですよ。僕のママも拍手してましたよ。「あんた、頑張ってるね」って(笑)。
Azumi かっこいい! 車とかバイクって、親への効力は大きいですよね。「こんなバイク買えるなんて、頑張ったんだね」みたいな。
高岩 間違いないですね。
——高岩さんは昨年、大型自動二輪免許を取られて、今は実際にハーレーに乗ってらっしゃるんですよね。
高岩 そうです。僕とSANABAGUN.のギターの隅垣元佐が免許取らせてもらいました。
Azumi そうなんだー、すごい! でも、むちゃくちゃ似合いますね。
高岩 去年の夏に、かっこいいところを地元の奴に見せたいから、1800cc近い、デカいハーレーで地元の岩手県宮古市に凱旋帰省したんですよ。僕のママも拍手してましたよ。「あんた、頑張ってるね」って(笑)。
Azumi かっこいい! 車とかバイクって、親への効力は大きいですよね。「こんなバイク買えるなんて、頑張ったんだね」みたいな。
高岩 間違いないですね。
 ——今回のライブは、どういったセットを予定されていますか?
Azumi 私はピアノ・デュオで、SWING-Oさんにピアノを弾いてもらいます。曲は自分のソロの楽曲やカバー、昔のユニットの曲をやるつもりでいます。
高岩 おー! それはバキバキの二人で、楽しみですね! 僕は若手ジャズマンのコンボで歌いますよ!
——―曲目はソロ・アルバムからやる予定ですか?
高岩 いや、多分スタンダードしかやらないですね。
Azumi スタンダード楽しみですね。私もスタンダードで何かやろうかな。対抗して。
高岩 やめてくださいよ!(笑)。
——今回のライブは、どういったセットを予定されていますか?
Azumi 私はピアノ・デュオで、SWING-Oさんにピアノを弾いてもらいます。曲は自分のソロの楽曲やカバー、昔のユニットの曲をやるつもりでいます。
高岩 おー! それはバキバキの二人で、楽しみですね! 僕は若手ジャズマンのコンボで歌いますよ!
——―曲目はソロ・アルバムからやる予定ですか?
高岩 いや、多分スタンダードしかやらないですね。
Azumi スタンダード楽しみですね。私もスタンダードで何かやろうかな。対抗して。
高岩 やめてくださいよ!(笑)。

Text:青山晃大 Photos:真弓 悟史
EVENT INFORMATION
<FREE[ER] WEEKEND PREMIUM LIVE SHOWCASE>
2018.10.13(土)、14(日) 代官山T-SITE GARDEN GALLERY 出演 13日 高岩遼、Azumi 14日 The ManRay、Rei、Kan Sano (acoustic set) 詳細はこちらCopyright (C) Qetic Inc. All rights reserved.